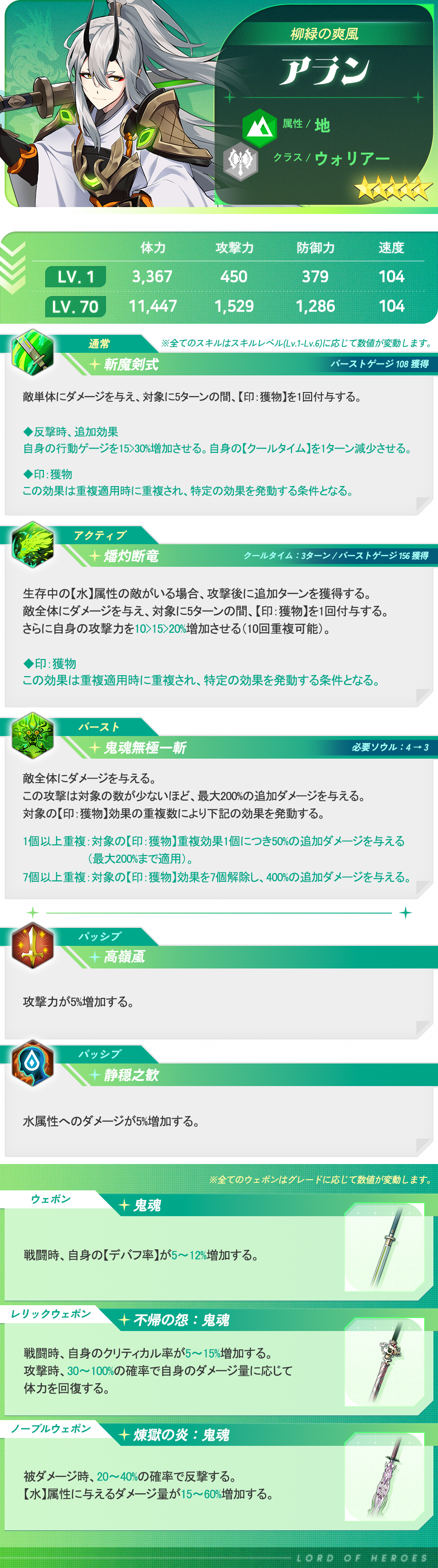低く吹き付ける高嶺颪。涼しい夏の夜の月暈。アランが覚えている幼い頃の放浪には、楽しい思い出しかなかった。もちろん、村に立ち寄るたび冷たい視線を浴びる理由、そして馬に餌を与えたり鞍の手入れをしている間、できるだけ目立たないようにしていた理由はいつもわからなかった。それでも生まれつきのんびりとした性格のおかげで、他人の些細な感情に振り回されることはなかった。なぜなら、この世で最も素晴らしい師匠と一緒にいられるなら、何でも耐えられると思っていたからである。だがしかし世の中の理とはいつも同じで、気持ちだけでは災難を防げない。
兆候はあった。後ろ指は刺されてもこれまで出入りを禁じられたことのなかった場所でさえ、一つまた一つと出入りを禁じられた。天子の継承が終わったという風の便りを耳にした頃、それが分岐点あった。息が詰まるような圧力が次第に迫ってきた。周りは冷淡そのものだった。伝承者である師匠のおかげでかろうじて守られていた心の防波堤が、まるで消えたかのようだった。そしてある日、ついに心の防波堤が決壊した。
アランは、荒れ狂う炎と消えゆく叫びの中で宇宙を見た。そして、巨大な神獣の理よりも、この経験が意味する師匠の決意に、胸がはち切れそうなほどの感情を抱いた。もし意識を失えば、それが最後だと思った。アランは必死に耐え、やっとの思いで冷たくなっていく師匠の手を握りしめた。その時、奇跡が起きた。差し伸べられた手は、似て非なる気配を感じた。
再び立ち上がったアランは、放浪を続けることを決意した。伝承者としての責任など、アランの道を阻むものではなかった。古臭い義務に縛られて生きるよりも分かれ道が来れば新たな旅を選ぶ旅人であることがアランにとっては重要であった。それに、今はもう旅をすることができない師匠に話す土産話もたっぷりと準備しなければならない。ある者は、どうしてそんなことを経験しても笑っていられるのかと問うかもしれないが、経験したことがどんなに重くても、笑うなという決まりはない。鬼人族アランの旅人の豪快な笑い声は、今日も周囲を温かく和ませてくれるだろう。かつて師匠が、そして友が、アランに教えてくれたあの微笑のように。