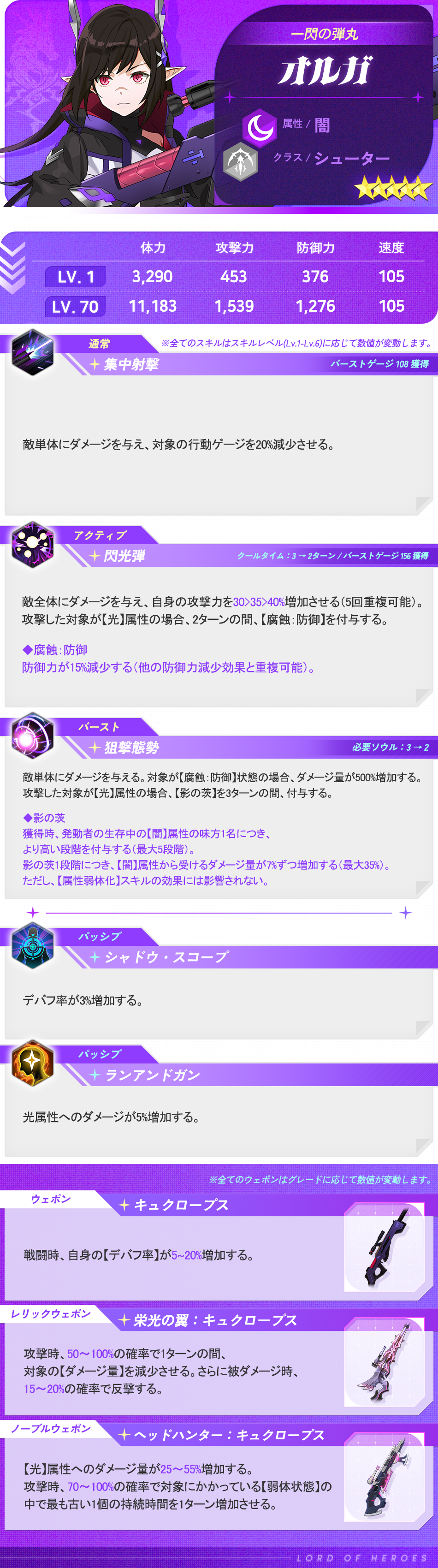レジスタンスの隠れ家は、遥か昔から廃墟と呼ばれし地であった。鼠を捕まえ、野良犬を追いかける子供たちがうごめく中で、ただ一人空を見上げる少女がいた。オルガが狙いを定めるのは、死肉を貪る鴉だった。空を舞う獲物を仕留められるなら、いつか帝国の太陽だって撃ち落とせるはずだ。
世界を救うという美しい建前の下で弱者を食い物にする者たちが、この廃墟には溢れかえっていた。希望を踏み躙る大人たちの偽善と、その狭間で生き延びようともがく子供たちの切実さは、「抵抗」という言葉の裏に潜む矛盾であった。オルガは現実への怒りと変革への意志を弾丸に込め、引き金を引いた。射撃の構えが定まるほどに、その覚悟は固まっていった。
王女との出会いは、オルガの世界観を根底から覆した。帝国の犬と思っていた王族の中に、自分以上に帝国を憎む者がいるなど想像もしなかった。立場は違えど志が同じなら手を組める、この発見は、周囲が猛反対する帝国研究員との危険な協力関係をも生み出した。
指名手配中の王女を庇って妨害工作を繰り返しても、帝国の攻勢は止まらなかった。突如として始まった空爆で隠れ家が崩れたとき、絶望の匂いが鼻をついた。全滅を覚悟したその瞬間、倒れていた仲間たちが次々と息を吹き返した。空襲兵器の「意図的な」不備、それはある可能性を示していた。あまりに都合のよい幸運の数々が、ついに一つの真実として姿を現したのだ。
仲間たちの反対を押し切って、オルガは絶妙なタイミングで現れた内通者を探り当てた。帝国中枢を崩壊させる鍵を握った今、最後の引き金を引く時が来た。かくして、一発の銃弾が皇帝の胸を貫いた。太陽は砕け散り、破壊に明け暮れた時代は静寂の中に沈んでいった。
だが頂点を極めた瞬間も、やがては過去となる。闇夜にも太陽の記憶は宿り続ける。勝利に酔いしれている暇はない。まずは瓦礫から街を建て直さなければ。暗闇の向こうで新しい夜明けを待ちながら…ひょっとすると、また運命が新たな出会いを運んでくるかもしれない。