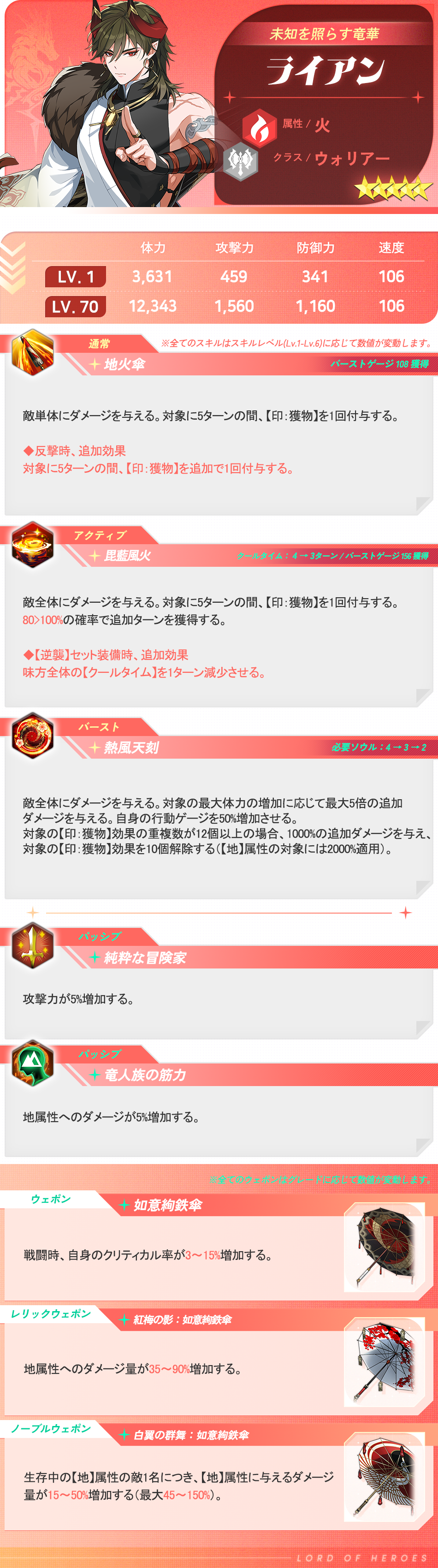日光浴をしてのんびり過ごしていたある日の事。ライアンは、アリの行列に小さな障害物を置いてみた。すると、アリたちはしばらく右往左往したものの再び列を整え、方向を取り戻した。しかし、一匹だけが仲間の列を離れ、おかしな方向へと進みはじめた。その小さな背を目で追った瞬間、ライアンの心にも新たな道が開けた。
出発の前に残した短い伝言を、ライレイが耳にすることはなかった。姉の怒りが荒野を覆いつくす頃、ライアンはすでにペルサを離れていた。食事と寝床を得るために身を寄せた放浪劇団での日々は数か月ほど続いた。生まれ持った力で物をねじ曲げ、あるいは軽々と持ち上げて見せるたび、観客からは歓声と拍手が湧き起こった。仕事は難しくなかったが、特別に楽しいわけでもなかった。華やかに見えて単調な暮らしに、飽きを覚えるのは自然なことだった。
やりたくないことから逃げるだけでは、最善の策とはいえなかった。心が動かぬままでは、どんなありふれたことにも意味は見いだせなかったからだ。真昼の陽射しの下で寝転び、峡谷や、雲、空を飛ぶ鳥の群れを眺める。ライアンは徹底して自らがやりたいと思うことだけに集中した。
その後の足取りは、さらに掴めなかった。恩人の家で農作業を手伝い、季節の巡りを肌で感じたかと思えば、幽霊が出ると噂される廃墟に滞在し、静寂と友になる夜もあった。旅は続いたが、彼はそこに教訓を求めはしなかった。ただあてもなく彷徨いながら、今いる場所、共にいる人々、そしてやりたいことだけに集中した。
もしかすると人生とは、一列に並んだ行列から抜け出した瞬間に始まるものなのかもしれない。海底王国を探すうちに時空の歪んだ塔へと迷いこんだのも、結局は偶然に身を任せた結果だった。塔で出会った懐かしくも新しい顔ぶれの中で、ライアンはまたひとつ、別の道の手がかりを見つけたのだ。この風変わりな道しるべは、今度はあなたの背を追って歩きはじめる。地図も持たず、寡黙な荷物持ちとして。